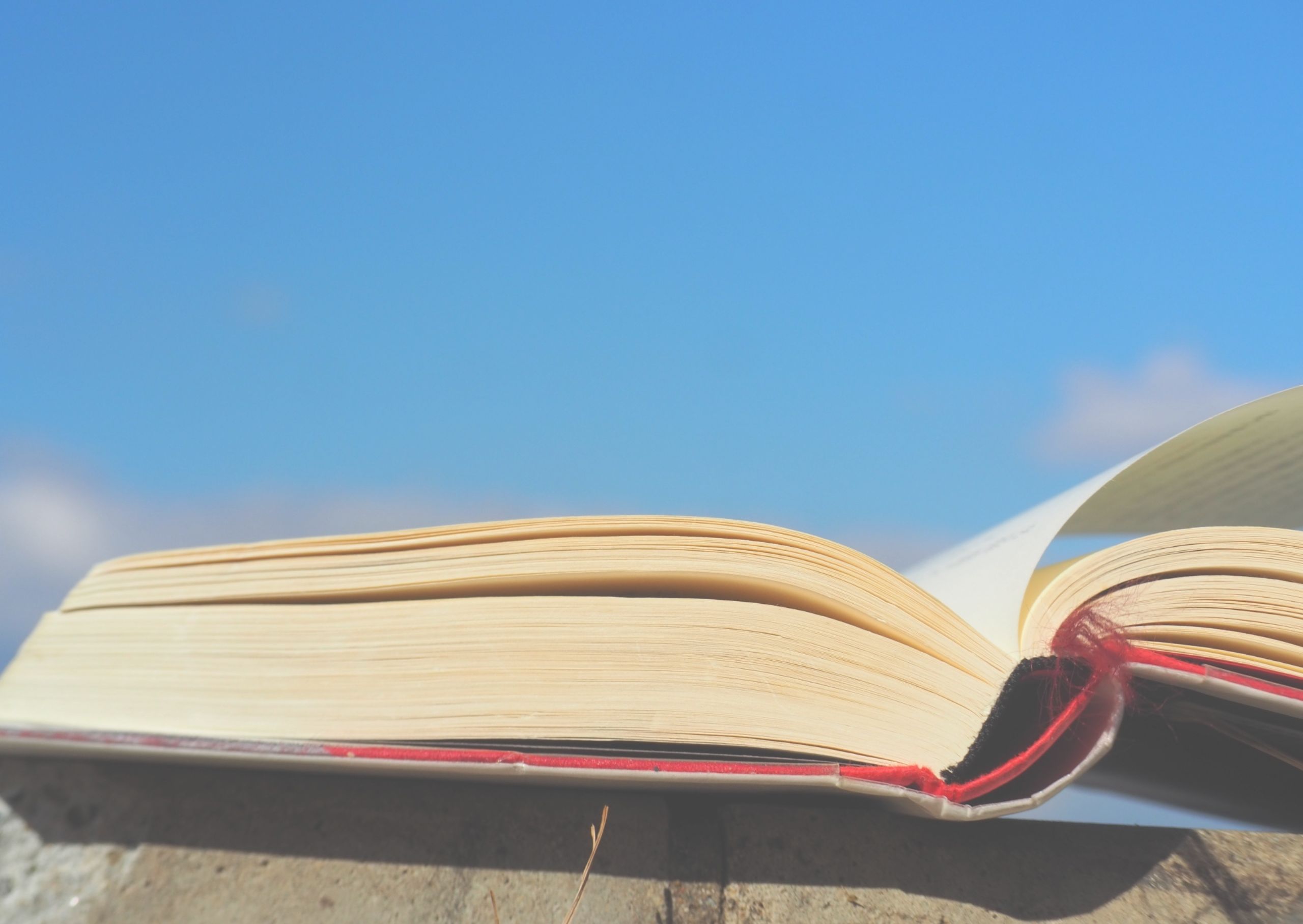はじめに
ほんの一年前まで読書会に参加したことはあっても、主催したことはありませんでした。気ままに参加したりしなかったり… 「読まなければ」と思って本に向かうのはニガテです。
もともと私は、読みたいと思って買い求めた本や図書館から借りてきた本が書棚にちょこんと置いてあって、何気なく手にとって読むのが好き。電車の中で読むのが好きですし、家族が寝静まったあとにお布団の中でモゾモゾしながら読むのも好きです。私にとって「ひとりで本を読む」というのは、至福のごほうび時間。なので、zoomが普及して、オンライン読書会があちこちで開催されるようになった頃、興味はあるけど「みんなで読む」というのがイメージできませんでした。
たしか人生で初めてのオンライン読書会は、5年ほど前にグリーフケアの学び場で行われていた「嫌われる勇気」が課題本の読書会でした。輪読しながら、主催者が内容を補足してくださり、理解を深めるといった読書会でした。
なので、読書会を主催する人は、その本に精通している!その分野の専門知識がある!という認知を持っていました。
私には無理…から一転
そんな認知を持っていた私ですので、「読書会の主催なんてとんでもないっ!!」と思っていたわけです。
ところが、ある時に出会った本を読み終えたとき、この感動を誰かとシェアし合いたい!!という衝動にかられました。
Amazon等の書籍購入サイトのレビューは手軽にその本を読んだ方の感想を知れますが、残念ながら一方通行。自分の感想をそこにアウトプットする勇気もなく、レビューを読めば読むほど、私が感動したポイントはここなんです!と誰かに聞いてほしくてムズムズ。
考えてみますと、私が遺族支援の取り組みで行っている”わかちあいの会”は、その時の自分が思っていることをただただそのままに言葉にしてみる場であり、耳を傾ける場。
精通もしていなければ、専門知識もないけれど、感想をシェアし合うなら私でもできる??
感動をシェアしあいたいという思いに背中を押され、おっかなびっくり状態ではありましたが、【センス・オブ・ワンダー】オンライン読書会を始めようと決めたのは2023年12月でした。
心配だったこと
主催するにあたって心配だったことは2つ。
・スケジュールを事前に提示する
・提示したスケジュールに開催する
両者とも当たり前のことですが、日程を決めた後に緊急度の高い用事が入ってきたらどうしよう…と思うと、2ヶ月、3ヶ月先の予定をFIXしてしまう怖さが私にはありました。なので偶然とはいえ、読書会をやってみたいと思うきっかけになった「センス・オブ・ワンダー」という本が短編作品だったことは、プレッシャーを感じすぎることなくトライできたように思います。
味をしめる
「センス・オブ・ワンダー」を読んでいるとき、私の脳裏にきまって浮かんだのは北八ヶ岳の森でした。
苔が美しく、森全体が神秘的な空気をまとっていて、鳥の鳴き声、風の通る音が耳に優しく入ってくる。
そんな体験をした森の中でこの本を読んでいるような錯覚に陥る。
「センス・オブ・ワンダー」を読むという体験は、私にとって自然の美しさや神秘にたくさん触れていた頃の私を慈しむ時間となりました。
読書会では、その日読んだページの中で、特に気になった箇所や響きを感じた部分をシェアし合いました。そうすると自分一人で読了したときには感じ得ない、作品や作者への畏敬の念というか、深まりを感じて、心がじんわりあったくなるんです。センス・オブ・ワンダー読書会2ヶ月目を終えたときに、読書会を続けていくことを決めました。
私にとって初めての読書会【センス・オブ・ワンダーオンライン読書会】は、2024年1月〜3月の3ヶ月間限定での開催でした。急遽の募集だったにも関わらず8名の方が参加くださいました。
次に選んだ本は
「死の受容過程」を説き、多くの人の最期を看取ってきた精神科医エリザベス・キューブラー・ロス(以下、キューブラー・ロス)と、ホスピスケアのスペシャリストのデーヴィット・ケスラーとの共著である【ライフ・レッスン】でした。グリーフケアの学びで、キューブラー・ロスを知り、彼女の本を何冊か読む中で出会いました。
ライフ・レッスンのページをめくると、こんな言葉に出会います。
「一生とよばれるこの時間のあいだには、学ぶべきさまざまなレッスンがある。とりわけ死に直面したひとたちとともいるとき、そのことを痛感する。死にゆく人びとは人生のおわりに多くを学ぶが、ほとんどのばあい、学んだ教訓を生かすための時間が残されていない。
「エリザベスからのメッセージ」より引用
わたしたちひとりひとりのなかにガンジーとヒトラーが住んでいる。もちろん象徴的な意味でだ。ガンジーは人間のなかにある最良のもの、もっとも慈悲ぶかいものをあらわし、ヒトラーは最悪のもの、人間のなかにある否定性と卑小性をあらわしている。人生のレッスンとは、みずからの卑小性にはたらきかけ、否定性をとりのぞいて、自己のなかにも他者のなかにもある最良のものをみいだす作業にかかわるものだ。
「エリザベスからのメッセージ」より引用
死に直面している人たちはいつも、大いなるレッスンをもたらす教師だった。なぜならば、生がもっともはっきり見えるのは、死の淵に追いやられたそのときだからだ。死にゆく人たちは自分自身が学んだレッスンを伝えることによって、生そのもののたいせつさについて多くを教えてくれる。
「デーヴィットからのメッセージ」より引用
二人のストレートな言葉に触れ、私はこの15のレッスンから、自分の人生を見つめ直してみたいと思ったのです。とはいえ、目次をみると戦々恐々とするレッスンが並んでいて、一人でやり抜ける自信はゼロ…
ということで読書会2冊目は、「人生のレッスンに一緒に取り組む仲間」と共に読み進めることにしました。
2024年4月にスタートして、今月は第十二章「明け渡しのレッスン」です。
スタート時点では20名近くの方がエントリーしてくださいましたが、毎月読書会に顔を出してくださるのは2〜4名です。
愛、人間関係、喪失、力、罪悪感、時間、恐れ、怒り、遊び、忍耐と読み進めてきました。この後、明け渡し、許し、幸福、最終レッスンと続きます。毎回、気づきと深い癒しがあって、人生のレッスンの虜になっています。
ゴールまで残り4レッスン。読み終えたとき、また最初から読み直したくなるような気がしていますが、少なくとも一年前より、一日一日をしっかり味わいながら生きている感じが私の中にあります。